私が彼と出会ったのは、かれこれ、40数年前のことであった。
未だ学生として、大学の文学部でフランス語とフランス文学を学んでいた頃に、初めて彼の事を知った。
彼は第一次世界大戦後、米国のロサンゼルスに住んで私立探偵をしていた。
彼が関わった事件は、7つの長編と幾つかの中編で、作家のレイモンド・チャンドラーにより紹介されている。
学生時代に憧れた「彼の姿」は、少し遠い世界の大人の間で交わされた、シンプルな時代のお伽話であったが、年齢と経験を重ねた私の中で「Playback」して、味わいを増している。
本を読むようになったキッカケ
小・中学から高校まで、読書感想文用を除き、ほとんど本を読まなかったが、「武器よさらば」や「誰がために鐘は鳴る」という米国映画をTVで観て、ヘミングウエイの世界に興味を持ったことがキッカケで、本を読むようになった。
少し渇いた感じがしたヘミングウェイの作品を読みながら、「ハードボイルド」という言葉を知ることになった。
「ハードボイルド」とは、第一次世界大戦後に「失われた世代(ロスト・ジェネレーション)」と呼ばれた作家群に共通した文体を意味している。
「ハードボイルド」は「Hardboiled egg」、つまり「硬くゆでた卵」から来ていて、「暴力的・反道徳的な内容を、批判を加えず、客観的で簡潔な描写で記述する手法・文体」と解されることが多いが、「暴力的・反道徳的な内容」というのは間違っていて、誤解を生じさせる。
同時に、タフな「私立探偵」が「酒場」と「暴力」に絡むストーリを「ハードボイルド」風とするのも誤っている。
「ハードボイルド」とは文体のこと
第一次世界大戦の頃まで、娯楽の主体であった舞台演劇から映画に、大衆の娯楽が移っていき、数多くの映画が作られ普及していく中で、人々はカメラを通した映像に慣れていく。
その映像は、人が肉眼で見るシーンそのものであるが、映像を捉えているのがカメラである故に、感情を交えず、つまり客観的で簡潔に描写されていく。これが「ハードボイルド」な表現と言われることになった。
「ハードボイルド」とは「カメラの眼(Camera eye)」で描かれた作品群であり、これは米国の作家に限らず、同時代の作家たち、例えばアルベール・カミュの「異邦人」なども含まれる。
フィリップ・マーロウとは?
フィリップ・マーロウは、地方検事局の捜査官をしていたが、命令違反で免職となり、ロサンゼルスで私立探偵を生業としていた。
タフな探偵ではあるが、決して暴力的ではなく、拳銃も滅多に手にしない。
フィリップ・マーロウがどんな男か、『高い窓』のあとがきで向井敏氏が書いている。
自分のやりたいようにやるタフで意地っ張りの探偵でありつつ、同時に「暗い夜に泣いている声を聞くと、何だろうと見に行かずにいられない」男。
そして、「タフな行動人と瀟洒なサロンの社交人とを、一身に兼ね備えた」男。
もう一つ加えると、昼下がりの開いたばかりの客が未だ入っていない酒場、空気も澄んでいてテーブルや椅子が綺麗に並んでいる。磨かれたカウンターの中で、少し緊張した面持ちでバーテンダーがグラスを磨きながら入って来る客を待っている。こういう緊張感ある静かな時間を愛している男。
「ぼくは店をあけたばかりのバーが好きなんだ。
店の中の空気がまだ綺麗で、冷たくて、何もかもがぴかぴかに光っていて、バーテンが鏡に向かって、ネクタイが曲がっていないか、髪が乱れていないかを確かめている。酒の瓶がきれいに並び、グラスが美しく光って、客を待っているバーテンがその晩の最初の一杯をふって、きれいなマットの上におき、折りたたんだ小さなナプキンをそえる。それをゆっくり味わう。静かなバーでの最初の静かな一杯ーーーこんな素晴らしいものはないぜ」
私は彼に賛成した。
『長いおわかれ』より 清水俊二氏訳
フィリップ・マーロウとは、そういう男である。
『Playback』のフィリップ・マーロウの忘れられない科白
7つの長編の中で数々の有名な、忘れられない科白を彼は呟いている。
彼が私たちの前に現れた最後の作品となった『Playback』の中の科白は、その中でも特に人口に膾炙している。
一夜を共にした、事件の発端となったヒロインとのシーン(『プレイバック』より 清水俊二氏訳)
「あなたの様に強い(hard)人が、どうしてそんなに優しく(gentle)なれるの?」
「しっかり(hard)していなかったら、生きていられない。やさしく(gentle)なれなかったら、生きている資格がない」
(If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.)
40数年前に彼に出会った頃、格好良いと憧れ、こういう男になれば素敵な女性と付き合えるのでは?と思っていた。
しかし、年齢と経験を重ね、こういう男と付き合う女性は僅少で、こういう男が幸せな生活・人生を送ることは難しいと分かってしまった。大人のお伽話に過ぎないと。
しかし、それでも尚、フィリップ・マーロウという「存在」について考えるとき、今の私は彼と友人になりたいと思っていることに気が付いた。年齢を重ね、この科白の意味、「やさしく(gentle)なれなかったら、生きている資格がない」が分かってきたからかもしれない。
こういう友人がいたら、どれほど心強く、グラスを傾けながら楽しく語り合えるだろうかと思う。
フィリップ・マーロウに権力は無い。むしろ権力から一番遠い位置にいて、出来る事と出来ない事を考えると、出来る事は僅かである。
しかし、「やって良い事」と「やってはいけない事」は弁えていて、矩をこえない。
問題は、私が彼と友人になりたいと願っても、彼が私を友人の一人に加えてくれるかどうか?という点である。
彼にとって、友人として私が相応しい「存在」であるかどうか?
もし、彼が私と友人になっても良いと思ったとしたら、彼はこう言うかもしれない。
「ルイ、これが美しい友情の始まりだな」
(Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.)
映画「カサブランカ」のラストシーンで、米国に亡命するため飛行機で去ったラズロとイルザを見送った後、お互いを認めながら敵対関係にあった酒場の主人のリックと警察署長ルノー(ルイ)が、夜の霧の中へ消えながら交わす科白。
救聖ボビー・ジョーンズは言っている。
「人生の価値は、どれほどの財産を得たかではない。何人のゴルフ仲間を得たかである」
フィリップ・マーロウがゴルフをプレイしたかどうかは知らないが、彼が『良いゴルフ仲間』なのは、間違いない。
今回は以上です。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。
気になった点や感想について、お気軽にコメントください。
良い記事と思われた方、『にほんブログ村ランキング』に参加してますので、ポチって頂けると嬉しいです。
↓
にほんブログ村
スポンサーリンク集






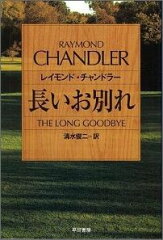

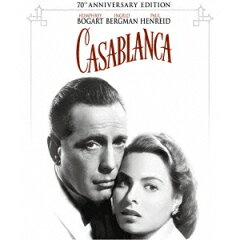
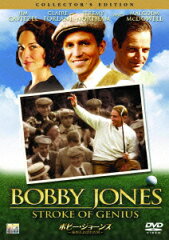


コメント